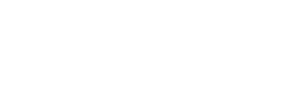
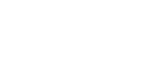
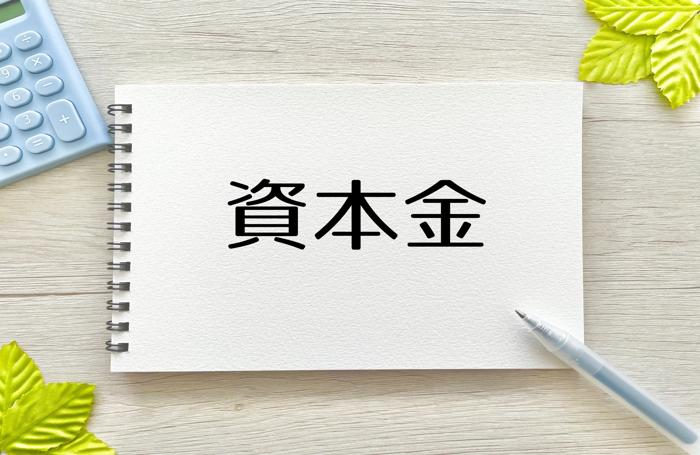
個人事業主が法人化する際に重要なのが、資本金の額をどう設定するかです。資本金は会社の元手となる資金であり、会社の規模や信用力を示す指標にもなります。法律上は1円から設立可能ですが、実際には初期費用や運転資金、信用面を考慮して決めることが大切です。ここでは、資本金の基礎知識や必要な金額の目安、決め方のポイント、払込方法などを解説します。

資本金とは会社が事業を始めたり、運営を続けたりするための「元手となる資金」を指します。会社設立時や法人化、増資時などに、経営者自身や出資者(株主、投資家など)から払い込まれたお金の合計額です。ここでは、資本金がどのようなものなのか、その特徴をご紹介します。
資本金は、会社を設立する際や事業を運営する際の基礎となるお金です。創業者自身の貯金や、第三者である株主・投資家からの出資が含まれます。
資本金は、会社の規模や財務基盤、信用力を示す代表的な指標の1つです。資本金が多いほど、会社の体力があると見なされやすく、取引先や金融機関からの信用度も高まります。
資本金は、銀行などからの借入金と異なり、資本金は返済義務がありません。会社の純資産として貸借対照表(バランスシート)の「純資産の部」に記載されます。
会社の業績とは無関係に金額が固定
会社がどれだけ利益を上げても、資本金の額は原則として変わりません。増資や減資の手続きを経て、初めて増減します。

法人化(会社設立)に必要な資本金は、法律上「1円」から可能です。2006年の会社法改正により、以前の「株式会社は最低1,000万円、有限会社は最低300万円」という最低資本金制度は撤廃されました。
ただし、実務上は「1円」だけで設立するケースはまれです。平均的な資本金額は、100万円~500万円未満が多い傾向がみられます。総務省や経済産業省の調査によると、設立時の資本金は「100万円~299万円」「300万円~500万円未満」が多く、1,000万円未満で設立する会社が大半です。

実際に資本金をいくらにするのか決める際には、以下のポイントを押さえることが重要です。
| ・初期費用と運転資金をカバーできるか ・業種や事業規模によって異なる ・社会的信用や取引先の印象を考慮する ・税制や許認可の要件を確認する ・資本金は後から増額(増資)・減額(減資)できる |
ここから、各ポイントについて解説します。
会社設立時には、登記費用や設備投資などの初期費用に加え、事業が軌道に乗るまでの運転資金(家賃、人件費、仕入れ、光熱費など)も必要です。一般的な目安として、「初期費用+3~6か月分の運転資金」を資本金として用意するのが推奨されています。
特に、売上が安定するまでに時間がかかる業種では、さらに多めに運転資金を見積もることも検討しなくてはなりません。
資本準備金とは、会社設立時に払い込まれたお金のうち、資本金に計上されなかった部分を指します。会社法では、払い込まれた資金の2分の1を超えない範囲で資本準備金として計上することが認められています。
例えば、設立時に1,000万円の出資があれば、最大500万円までを資本準備金とすることが可能です。資本準備金は、将来の損失補填や財務健全性の維持などに役立つが、資本金と異なり登記簿には記載されません。資本金と資本準備金をバランスよく設定することで、会社の信用力や財務安定性を高められます。
資本金の適正額は、業種や事業の規模に応じて大きく変動します。設備投資や仕入れが多い業種、従業員数が多い場合は、より多くの資本金が必要です。
例えば、建設業は500万円以上、不動産業は1,000万円以上、IT業は100~300万円程度が目安とされています。なお、一部の業種では法律や許認可で最低資本金が定められている場合があるため、事前に確認が必要です。
資本金は会社の信用力や体力を示す指標の1つです。資本金が少なすぎると、取引先や金融機関からの信用が低下し、大きな取引や融資が難しくなる場合があります。
取引先によっては、資本金額を取引条件としている場合もあるため、今後のビジネス展開を見据えて設定することが大切です。
資本金を1,000万円未満で会社を設立すると、設立から一定期間は消費税の免税事業者となるなど、税制上のメリットがあります。逆に1,000万円以上にすると、住民税均等割が高くなるなどのデメリットもあるため注意が必要です。
許認可が必要な業種(建設業、派遣業、不動産業など)は、一定額以上の資本金が求められる場合があるため、事前に要件を確認しておきましょう。
ここからは、資本金の増資と減資について解説します。
会社設立時に資本金を多く用意できない場合でも、事業拡大や信用力向上の必要が出てきた際に、株主や第三者からの出資を受けて資本金を増やすことが可能です。
増資には、会社の信用力や財務基盤の強化、資金調達力の向上といったメリットがあります。ただし、資本金が一定額を超えると税負担が増える場合や、株主構成が変わるリスク、手続きに費用がかかるなどのデメリットもあるため注意しなければなりません。増資の影響を十分に理解し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。
資本金の減額(減資)も可能です。減資は、累積赤字の補填や配当原資の確保、税負担の軽減(例:資本金1,000万円未満で消費税の免税事業者となる、1億円以下で外形標準課税の対象外となる)などの目的で行われます。
減資には、株主総会の特別決議や債権者保護手続きなど、慎重な手続きが必要です。ただし、減資によって会社の信用力が低下する可能性や、取引先・金融機関からの評価が変わるリスクもあるため、デメリットも十分に考慮する必要があります。

個人事業主が法人化して会社を設立する際、資本金の払込方法には以下のように明確な手順があります。
会社設立前は法人口座を開設できないため、発起人(設立者)個人の銀行口座を使用します。発起人が複数いる場合は、代表者(発起人総代)の口座を利用することが一般的です。
定款認証後、定款に記載した資本金の金額を、発起人の口座に払い込みます。払い込み方法は「振込」または「預入」があり、発起人が複数の場合は誰がいくら出資したか証明できるよう「振込」がおすすめです。発起人が1人の場合は、預入でも問題ありません。
資本金が確かに払い込まれたことを証明するため、通帳の表紙・表紙裏・振込記録が記載されたページのコピーを取ります。ネットバンキングの場合は、該当取引が分かる画面を印刷して用意します。
払込証明書には、払込金額の総額、払込があった株数、1株あたりの払込額、払込日、本店所在地、会社名、代表取締役の氏名などを記載します。正確な記載が求められます。
払込証明書と通帳コピーをまとめてホチキス留めし、会社の代表印(社印)で割印を押します。これによって、書類の一体性と正当性を担保することが可能です。
これらの書類を添付して法務局に登記申請を行います。払込が証明できない場合、法人登記ができないため、手続きには細心の注意が必要です。
資本金は一括でも複数回に分けて払込可能ですが、最終的に全額が払い込まれていることが必要です。払込後、資本金は設立前でも事業用の支払いに使えるが、登記完了まで再度払込できる状態にしておくと安心でしょう。
また、既存の個人口座で問題ありませんが、屋号付き口座は不可の場合があります。一連の手続きを正確に行うことで、スムーズに法人設立が進められるでしょう。
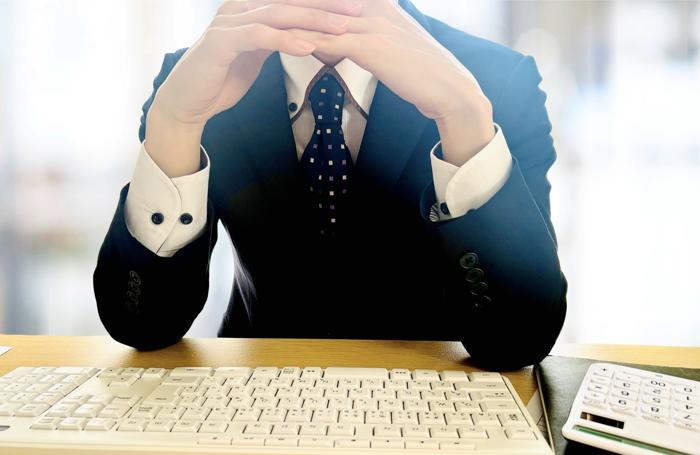
個人事業主が法人化する際、資本金は会社の元手となる資金であり、信用力の指標にもなります。法律上1円から設立可能ですが、初期費用や運転資金、社会的信用を考慮して決めることが重要です。資本金は後から増減可能で、払込には通帳コピーや払込証明書を準備しなくてはなりません。適切に手続きを行うためには、税理士などの専門家への相談も視野に入れましょう。
税理士を探す際には、税理士紹介ドットコムの活用がおすすめです。手数料なども一切不要で、北は北海道から南は沖縄まで、全国ご希望のエリアで税理士をご紹介することが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。