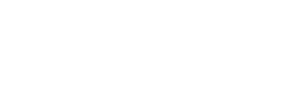
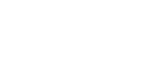

個人事業主が法人化を検討する背景には、事業の拡大や社会的信用度の向上、資金調達や人材採用の強化などがあります。法人化は基本的に1人から可能で、株式会社や合同会社など法人形態ごとの設立要件、社会保険・労働保険加入の義務、業種による許認可人数要件など、知っておくべきポイントも多いです。ここでは、個人事業主が法人化することによりメリット・デメリットや注意点を整理し、スムーズな法人化を進めるための基礎知識をご紹介します。

法人化(会社設立)は、基本的に「1人」から可能です。ここでは、株式会社と合同会社、その他法人形態にわけて、それぞれ解説します。
株式会社の設立は、発起人(出資者・設立手続きの実施者)1人でも可能です。取締役も最低1人いればよく、発起人・株主・取締役を同一人物が兼任できます。
以前は取締役会の設置が義務で、最低3人の取締役と1人の監査役が必要だったが、2006年の会社法改正以降はこの制約がなくなりました。ただし、取締役会を設置する場合は、取締役3人以上と監査役または会計参与1人以上(計4人以上)が必要です。
合同会社も「社員」(出資者)が1人いれば設立が可能です。ただし、ここでの「社員」は、一般的な従業員ではなく、会社の所有者・経営者を指します。
一方、合名会社も1人から設立可能です。合資会社は2人以上必要です。
会社設立自体は原則として「1人」から可能ですが、業種によっては事業開始に必要な許認可の取得条件として、設立時の人数が定められている場合があります。
例えば、一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)を始めるには、運転者5人と運行管理者1人の計6人が最低限必要です。発起人が1人でも、許認可取得のためには所定の人数を確保しなければなりません。
このほかにも、建設業、警備業、介護事業など、各種許認可業種では「役員」「管理者」「従業員」などの人数要件が設けられている場合があります。
許認可が必要な業種で会社を設立する場合、単に法人登記を終えるだけでなく、事業開始に必要な人数要件を満たしていないと許認可が下りず、実質的に事業を始めらません。設立後に人数を増やして許認可を取得することも可能ですが、最初から要件を満たす体制を整えておく方がスムーズでしょう。

個人事業主が法人化することで、以下のようなメリットが得られます。
| ・社会的信用度が高まる ・節税効果が期待できる ・経費計上の幅が広がる ・消費税の納付が2年間免除される ・欠損金(赤字)の繰越期間が長くなる ・事業承継や継続がしやすい ・有限責任となる |
ここから、各ポイントについて解説します。
法人化すると、登記簿謄本に情報が記載され、誰でも閲覧できるようになります。取引先や金融機関から「組織」として認識され、個人事業主よりも高い信用を得やすくなるのがメリットです。結果として、融資や新規取引の獲得、優秀な人材の採用がしやすくなるなど、事業拡大のチャンスが広がるでしょう。
法人化によって、所得税から法人税へと課税方法が変わります。所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率も上がりますが、法人税は一定の税率で計算されるため、所得が大きくなるほど節税効果が高まるのが特長です。
また、役員報酬や退職金を損金算入できる、家族に役員報酬を支払って所得分散ができるなど、さまざまな節税策も使えるようになります。
法人化すると、個人事業主のときよりも経費として認められる範囲が広がります。例えば、役員報酬や法人名義の生命保険料、福利厚生費などが経費として計上できるため、課税所得を抑えることが可能です。
法人設立時の資本金が1,000万円未満であれば、設立から2年間は消費税の納付が免除されます。(一定条件あり)個人事業主として売上が1,000万円を超えた場合、本来は2年後から消費税の納税義務が生じますが、法人化すれば新たに2年間の免除期間が得られるのも大きなメリットです。
個人事業主の場合、青色申告で赤字を繰り越せる期間は3年ですが、法人の場合は最大で9~10年まで繰り越せるのがメリットです。
将来的に黒字化が見込まれる場合、過去の赤字を長期間にわたって相殺できるため、節税につながります。
法人は「法人格」として独立した存在であるため、代表者が交代しても事業そのものは継続できます。個人事業主の場合、事業主が亡くなったり、引退したりすると廃業になることが多いですが、法人であれば事業承継が容易でしょう。
法人化すると、出資額の範囲でしか責任を負わない「有限責任」となります。個人事業主は無限責任のため、事業で発生した債務を全て個人で負担する必要があるが、法人の場合は原則として会社の財産の範囲内で責任を負うのが特長です。
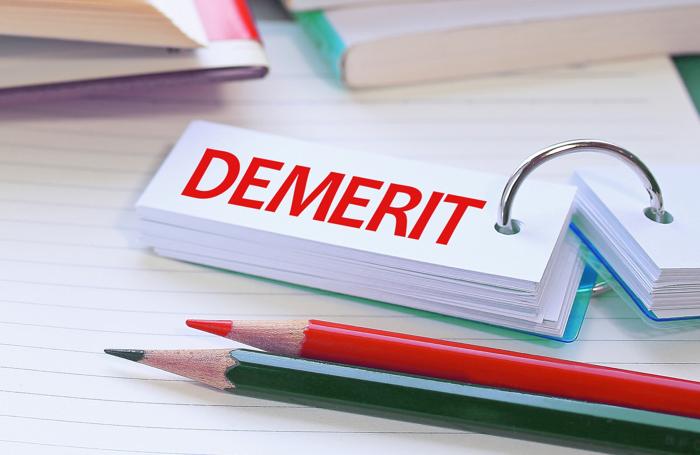
個人事業主が法人化する際には、以下の点に留意しなくてはなりません。
| ・設立や解散に費用と手間がかかる ・社会保険への加入義務が発生しコストが増加 ・赤字でも税金(均等割など)の納付義務がある ・事務作業や会計処理の負担が増える ・プライベートで使えるお金が制限される |
ここから、それぞれの内容を確認しておきましょう。
法人設立には、株式会社なら登録免許税や定款認証手数料などで約22万~24万円、合同会社でも10万円以上の費用が発生します。また設立時だけでなく、法人を解散する際にも解散登記や清算人の登記などの費用が必要手続きも複雑で、専門家への依頼が必要な場合、その報酬もかかることを覚えておきましょう。
法人化すると、代表者1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金など)への加入が義務づけられます。保険料は会社と従業員(代表者含む)で折半となり、従業員が増えるほど会社負担も大きくなるのがデメリットです。個人事業主時代よりも社会保険負担が重くなる傾向がみられます。
法人は、たとえ赤字でも法人住民税の均等割など最低限の税金を納める必要があります。個人事業主の場合、赤字なら所得税や住民税は納付不要なケースもあるが、法人では必ず一定額の税負担が発生する点に注意しなくてはなりません。
法人になると、決算書や法人税申告書の作成、定款の管理など、個人事業主時代よりも事務作業が格段に煩雑になるのがデメリットです。税理士や会計士に依頼するケースも増え、コストや手間が増加します。また決算期には、申告や納付の期限も厳格に管理しなくてはなりません。
法人の資産と個人の資産は明確に区別する必要があり、会社の利益を自由に引き出せません。役員報酬や配当など、正規の手続きを経て受け取る必要があり、個人事業主時代のような柔軟性は失われます。
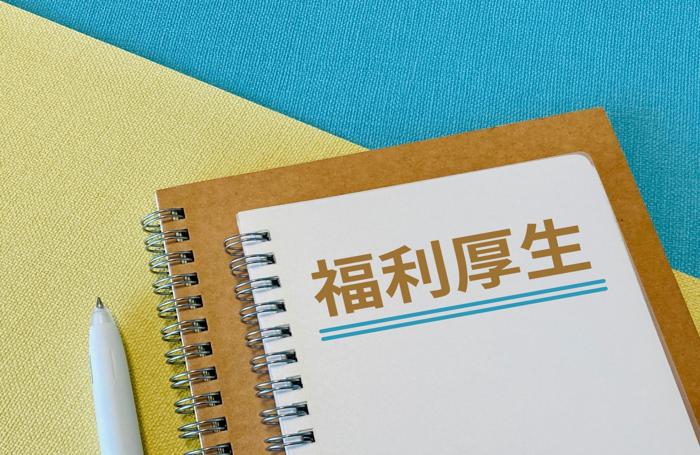
法人化すると、社会保険と労働保険の加入義務が発生する人数やタイミングは、それぞれ異なります。
| 保険の種類 | 法人の場合の加入義務発生人数 | 備考 |
| 社会保険(健康・厚生年金) | 0人(役員のみでも義務) | 法人設立と同時に強制適用 |
| 労働保険(労災・雇用) | 労働者1人から | 労災は全員、雇用保険は条件あり |
ここから、社会保険と労働保険の加入義務を、それぞれ解説します。
法人(株式会社・合同会社など)の場合は、人数に関係なく強制適用されるのが特長です。役員のみ、従業員ゼロでも、法人設立と同時に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が発生します。役員報酬が支給される場合、その役員も被保険者となるのが特長です。
一方、個人事業主の場合は、常時5人以上の従業員を雇用する場合に強制適用となる
5人未満の場合は任意適用されます。(一部業種を除く)
労働者(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用した時点で、法人・個人問わず加入義務が発生します。労災保険は、雇用形態や人数に関係なく、1人でも労働者を雇えば強制適用されるのが特長です。
雇用保険は、31日以上雇用の見込みがあり、かつ週20時間以上働く従業員がいる場合に加入義務が生じます。役員のみの場合は、労働保険の加入義務はありません。

個人事業主の法人化は基本1人から可能です。法人化により社会的信用度の向上や節税効果など多くのメリットが得られますが、設立費用や社会保険負担増加などのデメリットもあります。業種によっては許認可取得に人数要件がある場合もあることや、法人化後は役員のみでも社会保険加入義務が発生するなど、注意しなくてはならない点も多いのが特長です。そのため法人化の際には、税理士などの専門家に相談するのが賢明です。
税理士を探す際には、税理士紹介ドットコムの活用がおすすめです。手数料なども一切不要で、北は北海道から南は沖縄まで、全国ご希望のエリアで税理士をご紹介することが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。