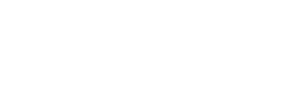
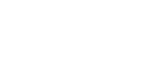
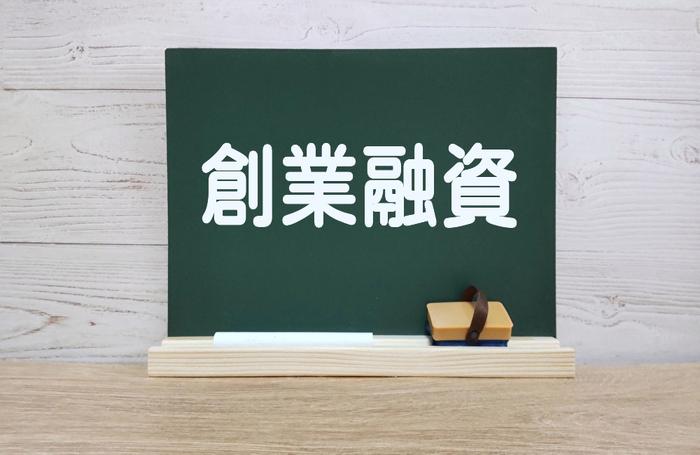
脱サラをして起業を目指す方にとって、資金調達は大きな課題です。そこで活用したいのが「創業融資」や各種の補助金・助成金制度でしょう。日本政策金融公庫の創業融資は、無担保・無保証・低金利といった魅力的な条件でスタートアップを支援してくれます。
本記事では、その概要やメリット、申請の流れに加え、創業時に使える代表的な補助金・助成金についてもご紹介します。
目次

そもそも、日本政策金融公庫の創業融資とは、どのような制度なのでしょうか。ここでは、創業融資の制度概要やメリット、取得条件、申請の流れをご紹介します。
日本政策金融公庫の創業融資とは、新たに事業を始める人や創業から間もない事業者を支援する制度です。特に、新規開業者や中小企業にとって非常に有利な条件で資金調達できます。おもな融資は「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」、「再挑戦支援資金」の3つです。
無担保・無保証、低金利、長い返済期間などが特徴で、創業者が安心して事業を展開できる環境を提供しています。新規開業資金は、新たに事業を始める方や、創業からおおむね7年以内の事業者が対象となっているのが特徴です。さらに、設備資金と運転資金の両方に使えます。
女性、若者/シニア起業家支援資金は、特定の対象者に優遇される融資です。一方、再挑戦支援資金は創業に再挑戦する方を支援する融資です。
創業融資を活用するメリットは、以下のとおりです。
| ・融資が受けやすい ・無担保・無保証の融資が受けられる ・低金利、かつ返済期間が長い ・特別利率を適用できる ・事業計画書の支援が受けられる ・民間金融機関からの信用度が向上する |
ここから、各メリットの内容を解説します。
日本政策金融公庫は中小規模の事業者や創業を支援するために設立されています。そのため、民間の金融機関に比べて融資を受けやすい傾向があるのはメリットです。
創業融資は、多くの融資制度が無担保・無保証で提供されており、創業者が安心して資金調達が可能です。特に新規開業資金では、事業開始後2期分の税務申告が終わっていない場合でも無担保・無保証で融資を受けられます。
金利が低く、返済期間も長いため、資金繰りがしやすくなる点も、創業融資を活用するメリットです。例えば新規開業資金では、設備資金は最長20年、運転資金は最長10年までの返済期間を選択できます。
女性や若者、シニアなど特定の条件を満たす起業家には特別利率が適用され、さらに優遇されることがあります。
日本政策金融公庫から事業計画書の作成や経営アドバイスが提供されるため、創業者が実現可能な計画を立てやすくなる点もメリットです。
日本政策金融公庫からの融資を受けることで、将来的に民間の金融機関からの融資も受けやすくなる可能性があります。起業まもない企業にとって信用向上につながるのは、大きなメリットだといえるでしょう。
日本政策金融公庫の創業融資には、以下の5つの審査基準があります。
| ・自己資金が十分にあること ・自己資金に見せ金がないこと ・起業する業種での経験が十分であること ・信用情報に問題がないこと ・事業計画がしっかりしていること |
自己資金が十分にあると、事業に対する計画性があり、非常事態の資金も確保できていると判断されます。一般的には、創業資金の総額に対して3割程度が目安です。
また、自己資金に見せ金がないことを確認しなくてはなりません。起業する業種での経験が6年以上あると良好とされますが、例外もあるため注意が必要です。例えば、フランチャイズで起業する場合などは、経験がなくてもサポートを受けられるでしょう。
信用情報に問題がないこと、実現可能な事業計画を準備することも必要です。さらに、2024年4月から「新規開業資金」制度が拡充されました。この制度は以下の特徴があります。
| ・対象者:新たに事業を開始する方、または事業開始後おおむね7年以内の方 ・融資限度額:最大7,200万円(うち運転資金は4,800万円まで) ・担保や保証人:原則として不要ですが、希望に応じて相談可能 ・自己資金要件:自己資金の明確な定義は設けられていないが、特定の条件下では緩和されることがある |
創業融資を申請するためには、以下のステップを踏む必要があります。
まず、窓口かインターネット経由で申し込みを行います。それぞれのやり方は、以下のとおりです。
| ・窓口での申し込み:創業地や創業予定地の近くの日本政策金融公庫の支店で相談予約を取り、必要な情報を確認しましょう。電話で予約を取り、窓口で相談を行います。 ・インターネット申し込み:日本政策金融公庫のホームページから24時間いつでも申し込みが可能です。メールアドレスを登録し、届いたメールに記載されたURLからフォームを入力して送信しましょう。 |
必要書類は、創業計画書、見積書、許認可証、運転免許証またはパスポートなどです。インターネット申し込みの場合は、これらの書類を電子データで用意しなくてはなりません。
個人事業主の場合、最近2期分の確定申告書や収支内訳書も必要です。法人の場合は、履歴事項全部証明書や登記簿謄本も準備する必要があります。
申し込み後は、日本政策金融公庫の担当者との面談が必須です。面談の日程は担当者と相談して調整しましょう。審査結果は約2週間で通知され、融資が決定した場合は後日借用証書が届きます。
契約手続きを終えると、指定された口座に借入金が入金されます。申請時には、税理士などの専門家のサポートを受けることがおすすめです。
必要書類のチェックや面談の対策など、専門家のサポートを受けることで審査通過率を高められるでしょう。必要書類を事前に準備し、申し込み手続きをスムーズに進めることも大切です。

創業融資以外にも、創業時に使える補助金や助成金がいくつかあります。ここでは、おすすめのものを5つご紹介します。
ものづくり補助金とは、中小企業や小規模事業者が革新的サービス開発や生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する制度です。正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」で、税金を基に実施されています。
中小企業や小規模事業者が対象で、資本金や従業員数に基づく条件があるのが特徴です。特定非営利活動法人や社会福祉法人も含まれます。日本経済の競争力強化と持続的発展を目指し、生産性向上、新製品開発、高付加価値化、グリーン化を推進する事業が採択対象で、補助率・金額は、中小企業が1/2、最大2,500万円(高付加価値化枠)または3,000万円(グローバル枠)です。
参考:ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が持続的に事業を運営するための補助金で、賃金引上げや創業を支援します。2025年は経営計画の策定を重点化し、申請枠が整理・簡素化されています。
資本金が5億円未満の法人や個人事業主が対象で、医師や協同組合などは除外です。補助率は、一般型が2/3、最大50万円、創業型は2/3、最大200万円、特例を活用すると最大250万円まで増加します。
東京都創業助成金とは、東京都内での新たなビジネスの立ち上げを支援する制度です。申請者には、経営経験や創業支援事業の利用状況といった特定の要件があります。
東京都内で創業を計画する個人や法人で、経営経験が5年未満の者が対象で、特定非営利活動法人も含まれる点が特徴です。補助率・金額が2/3以内、100万円から400万円の範囲で支援されます。
参考:東京都創業NET/創業助成金(東京都中小企業振興公社)
事業再構築補助金は、新型コロナ禍で創設された補助金で、事業の再構築や拡大を支援します。中小企業や中堅企業で、特定の要件を満たす事業が対象です。
事業の再構築や拡大を支援し、経済の回復を促進します。補助率・金額は100万円から5億円までの範囲です。
IT導入補助金とは、ITツールの導入を支援し、デジタル化を促進する補助金です。中小企業や小規模事業者で、業務のデジタル化を目的とするものが対象です。
業務のデジタル化を目的とするソフトウェアやシステムの導入を支援することで、生産性の向上を実現できるでしょう。補助率・金額は、A類型が5万円以上150万円未満、B類型は150万円以上450万円以下で、補助率は1/2以内です。

補助金や助成金を活用して、創業当時の資金繰りを行う場合、以下のポイントを押さえなくてはなりません。
| ・事前の要件確認が重要 ・計画書の完成度が審査に影響 ・計画書の完成度が審査に影響 ・申請後のスケジュール管理 ・複数制度の併用は要注意 |
ここから、それぞれの内容を確認しておきましょう。
補助金や助成金には、対象者や利用目的、申請条件が細かく設定されています。そのた、め、申請を始める前に募集要項やガイドラインを熟読し、必要な条件を満たしているか確認することが不可欠です。不明点があれば、実施機関に問い合わせましょう。
申請書類には、過去の業績や新たに挑戦する事業計画を明示した書類が必要です。事業モデルを具体的に示すことも求められます。計画書の完成度が審査結果に大きく影響するため、十分に準備することが大切です。
申請後は、事業の進捗を適切に記録し、定められた報告義務を確実に果たすことが求められます。これらの義務を怠ると、受給した補助金の返還を求められることがあるため注意しなくてはなりません。
補助金や助成金は原則として後払いであり、すぐには支給されないことも覚えておく必要があります。申請から支給までに時間がかかるため、自己資金や運転資金をあらかじめ確保しておくことが重要です。
補助金や助成金は複数の制度に申請することは可能です。しかし、同じ目的で併用することはできません。例えば、同一の設備に対する支援金は、いずれか1つに限られます。

脱サラして起業を目指す際は、日本政策金融公庫の創業融資が資金調達に有効です。無担保・無保証・低金利が特徴で、事業計画書の支援も受けられます。また、創業時には「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」などの各種助成制度も活用可能です。条件確認や計画書作成、申請後の管理が成功の鍵といえるでしょう。そのため、税理士などの専門家への相談も視野に入れることをおすすめします。
税理士を探す際には、税理士紹介ドットコムの活用がおすすめです。手数料なども一切不要で、北は北海道から南は沖縄まで、全国ご希望のエリアで税理士をご紹介することが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。