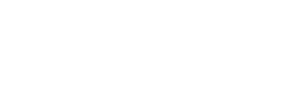
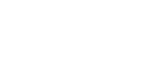
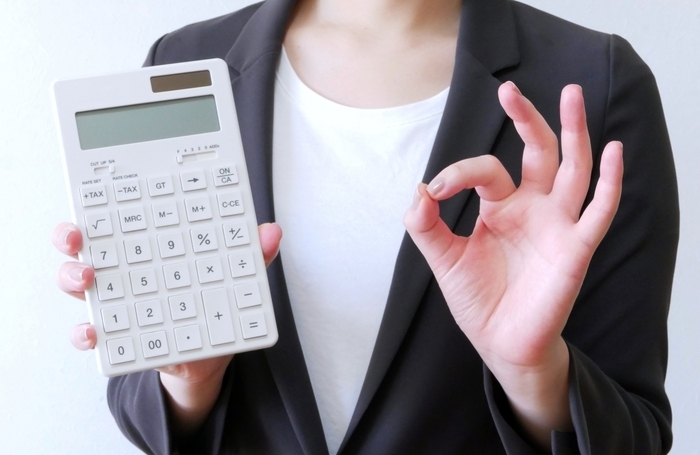
個人事業主にとって、事業の安定運営と利益確保のためには「経費の見直しと削減」が欠かせません。しかし、経費の計上にはルールがあり、無理な節税は税務リスクを招く可能性もあります。
ここでは、日々の支出を見直しながら節税につなげる実践的な経費削減テクニックを10項目に厳選してご紹介します。また、どこまでが経費として認められるのかという判断基準や、やりすぎた場合の注意点・ペナルティについてもわかりやすく解説します。

そもそも、個人事業主の経費とは、どのようなものが該当するのでしょうか。ここでは、経費計上により節税につながる理由と、経費計上の可否判断基準をご紹介します。
経費を計上することで節税につながる理由は、課税所得を減らせるためです。課税所得は「収入-経費」で算出されるため、経費を増やすと課税対象となる利益が減少し、結果として納税額が軽減される仕組みです。
例えば、収入が500万円で経費が100万円の場合、課税所得は400万円となり、経費なしの場合に比べて税負担が軽くなります。この仕組みによって、事業主は手元に残る資金を増やし、キャッシュフローを確保することが可能です。
また、経費として認められる支出は事業に関連するものである必要があります。適切に経費計上を行うことで、税務署からの指摘を防ぎつつ、節税効果を最大化できるでしょう。
経費として認められるかどうかの判断基準は、以下のとおりです。
経費は事業運営に直接関係する支出である必要があります。例えば、取引先との会食や業務用の備品購入などは事業との関連性が高いため認められます。一方で、プライベートな支出(家族との外食など)は認められません。
個人的な趣味や娯楽に関する支出は経費として計上できません。また、個人にかかる所得税や住民税なども対象外です。
領収書やレシートなどの証拠書類を適切に保管し、支出内容を客観的に説明できる状態にしておかなくてはなりません。これによって、税務調査への対応が可能になります。
経費として計上する金額が、常識的な範囲内であることも重要です。売上に対して不釣り合いな高額の経費は、不正や脱税の疑いを招く可能性があります。
自宅や車など事業とプライベートで共有しているものについては、家事按分を利用して事業利用分のみを経費として計上しなくてはなりません。割合は使用面積や使用時間など、合理的な根拠に基づいて算出します。

個人事業主が経費を削減するテクニックは、以下のとおりです。
| ・事業に関わる支出を見直し経費化する ・業種ごとの経費対象を正しく把握する ・少額減価償却資産の特例を活用する ・短期前払費用の特例を利用する ・税金や保険料も経費として活用する ・小規模企業共済やiDeCoに加入する ・ふるさと納税や医療費控除を活用する ・扶養控除や所得控除を最大限利用する ・法人化を検討する ・帳簿管理を徹底し、申告漏れ ・無申告を避ける |
ここから、それぞれのテクニックの内容を解説します。
家事按分とは、事業とプライベートの両方で使用する支出を一定の割合で分け、事業分を経費として計上する方法です。例えば、自宅で業務を行う場合、家賃や光熱費、通信費などの一部を経費化できます。具体的な按分方法としては、使用時間や使用日数を基準に計算することが一般的です。事業に直接関係する部分だけを経費として計上でき、節税につながります。
業種によって必要経費は異なります。例えば、飲食業では食材や調理器具が対象となり、IT業ではソフトウェアや通信費が重要です。自分の業種に適した経費項目を把握し、漏れなく計上することで節税効果を最大化できます。また、経費の範囲や上限についても確認し、不適切な計上を防ぐことが重要です。
少額減価償却資産の特例では、30万円未満の資産を購入した場合、一括で経費計上が可能です。この制度は青色申告者が利用でき、通常の減価償却よりも早期に節税効果を得られるメリットがあります。また、10万円未満の備品は消耗品費として扱われ、一括計上が可能です。そのため、資金繰りの効率化も期待できます。
短期前払費用の特例とは、翌年分の保険料や家賃などを前払いした場合でも、その年の経費として計上できる制度です。支払日から1年以内にサービス提供を受ける場合に適用されます。ただし、初年度には大きな節税効果が期待できますが、翌年度以降には注意が必要です。
個人事業税や固定資産税などの税金、および火災保険料や自動車保険料など業務に関連する保険料は経費として認められます。ただし、プライベートと混在している場合は家事按分が必要です。これらを正確に処理することによって、所得控除額を増やし節税につなげられます。
小規模企業共済とiDeCoは掛金が全額所得控除されるため、高い節税効果があります。小規模企業共済は廃業時にも共済金を受け取れる安心感があり、iDeCoは資産運用による増加も期待できるのがメリットです。併用すれば年間最大165万円以上積み立てることが可能で、老後資金の準備と節税効果を両立できます。
ふるさと納税は寄付額に応じた控除が受けられる制度であり、地域貢献と節税が同時に可能です。また、医療費控除は年間医療費が一定額を超えた場合に適用されます。両者を併用すると控除額が影響し合うため、シミュレーションによる最適な寄付額設定が重要です。
扶養控除は年間所得48万円以下の親族が対象となり、配偶者控除などと併せて利用すると税負担軽減につながります。また、生命保険料控除や地震保険料控除なども、忘れず申請しましょう。これらの控除制度を最大限活用することで、所得税率を下げることが可能です。
事業規模によっては、法人化による節税効果が期待できます。法人化すると役員報酬への給与所得控除や従業員退職金の損金計上などが可能となり、個人事業主よりも柔軟な節税対策が取れます。ただし、法人設立にはコストもともなうため、慎重な検討が必要です。
帳簿管理は、正確な申告と節税対策の基本です。不十分な帳簿では経費否認リスクが高まり、加算税や延滞税など余計な負担につながります。また無申告の場合にはさ、らに厳しいペナルティが課されるため、定期的な記帳と書類保存が重要です。

法人化すると、住居や車両関連費、福利厚生など幅広い支出が経費として認められるようになります。一方で、個人事業主の場合はプライベートな支出や自己への支払いについて厳しい制限があるため、按分や用途の明確化が必要です。
これらの違いを理解し、自身の状況に応じた適切な選択を行うことが重要だといえます。ここから、主な項目の違いをご紹介します。
法人名義で契約した住居(社宅)であれば、家賃の5割から8割程度を経費として計上可能です。一方、個人事業主で自宅兼事務所の場合、事業利用部分のみ(2~5割程度)を按分して経費計上できますが、全額を経費にはできません。
法人代表者の役員報酬や従業員への給与は、経費として計上可能です。しかし、個人事業主の収入は「給与」ではなく「事業所得」として扱われるため、自分自身への支払いを経費にできません。また、生計を一にする家族への給与も原則経費にできないため注意が必要です。(ただし、青色申告専従者給与として届出を行った場合は例外あり)
福利厚生費
法人の場合、従業員や役員(法人代表者)に対する福利厚生費(健康診断、社員旅行など)は、広く経費計上が認められています。一方、個人事業主の健康診断や、プライベートな支出は福利厚生費として認められません。
法人の場合、役員や従業員に支払う退職金は経費に計上できます。しかし個人事業主の場合、自分自身への退職金という概念がないため、経費計上できません。
法人名義で購入した車両にかかるガソリン代、保険料、車検代などの諸費用は全額経費計上可能です。個人名義の車両の場合、事業利用部分のみ按分して経費計上できます。つまり、プライベート利用部分は対象外です。
法人契約の生命保険料は一定条件下で経費計上できます。個人事業主の場合、生命保険料控除として所得控除の対象にはなりますが、経費にはできません。
法人の場合、役員や従業員に支払う出張手当は、規定に基づいて経費計上可能です。一方、個人事業主の場合は、自分自身への出張手当という形での経費計上は認められません。

個人事業主が、過度な経費計上を行うのは、以下のようなリスクが発生するため避けるべきです。
| ・税務調査と追徴課税 ・資金繰りやキャッシュフローへの影響 ・銀行融資やローン審査への影響 |
ここでは、それぞれの内容とリスク回避のためのポイントをご紹介します。
誤ったものを経費計上すると、税務調査と追徴課税のリスクが発生します。
経費が過剰に計上されると、税務署から「不自然な動き」と見なされ、税務調査が入る可能性が高まります。特に、事業に関係のない費用やプライベートの支出を経費として計上すると、ほぼ確実に不正が発覚するため注意が必要です。
不適切な経費計上が発覚した場合、以下のようなペナルティが科されます。
| ・過少申告加算税:不足分の10〜15%が課税される ・重加算税:悪質な場合、本税の35〜40%が追加で課税される |
税務調査では過去数年分の申告内容まで遡って調査されるため、多額の追加納税を求められる可能性があります。
過度な経費計上は一時的に節税効果を得られるものの、結果的に手元に残る資金が減少します。したがって、資金繰りが厳しくなるのはリスクです。
経費を多く計上すると所得が低く見えるため、銀行などから融資を受ける際に不利になる可能性があります。所得が低いと返済能力がないと判断され、ローン審査に通らない場合もあるでしょう。
ここまでにご紹介したリスクを回避するためには、以下の点を踏まえ、適切かつバランスの取れた経費計上を心がけなくてはなりません。
| ・経費は事業関連のみを計上し、不明確な支出は避けること ・領収書や証憑書類を保管し、経費内容を合理的に説明できる状態にしておくこと ・家事按分など曖昧になりやすい項目については正確な割合で計算すること ・税理士など専門家に相談し、適切な経費計上を行うこと |

経費削減は、個人事業主が手元資金を確保し、安定した経営を続けるための重要な手段です。ただし、節税を意識するあまり無理な経費計上を行うと、税務調査や資金繰りの悪化といったリスクもともないます。今回、ご紹介したテクニックや注意点を参考に、事業実態に即した適切な経費管理を心がけ、健全な経営と将来への備えを両立させていきましょう。また、税理士などの専門家に相談することも有効な手段です。
税理士を探す際には、税理士紹介ドットコムの活用がおすすめです。手数料なども一切不要で、北は北海道から南は沖縄まで、全国ご希望のエリアで税理士をご紹介することが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。