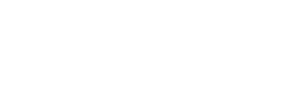
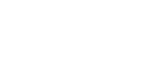

「資本金が少なくても会社を作れるの?」と疑問に思う方に向けて、本記事では「1円起業」という制度をご紹介します。会社法改正により、資本金1円から株式会社や合同会社を設立できるようになり、起業のハードルは大きく下がりました。しかし、実際には設立費用や運転資金が必要で、信用上のリスクも存在します。ここでは、1円起業の仕組みや条件、手続きの流れ、メリットとデメリット、注意点までわかりやすく解説します。
目次

1円起業とは、会社法改正により資本金1円から株式会社や合同会社を設立できるようになった制度です。ここから、どのような制度か詳しく解説します。
2006年の会社法改正により、株式会社・合同会社設立時の「最低資本金制度」が撤廃され、1円以上で設立が可能となりました。改正の目的は、起業の促進や資金調達ハードルの低減、ベンチャー育成など経済活性化政策の一環です。
現在、株式会社も合同会社も資本金1円から設立することが可能です。合同会社は2006年の会社法施行で新設された形態で、少額資本・個人設立に向いています。

1円起業ができる条件は、以下のとおりです。
| ・株式会社・合同会社の設立に必要な基本書類を整えること ・定款認証や登記費用(数万円程度)を支払えること ・実際の事業資金や運転資金を用意できること |
ここから、それぞれについて解説します。
会社の設立には「定款」「印鑑」「発起人や役員関連書類」「資本金の払い込み証明書」など、基本書類を整える必要があります。定款作成・認証や各種届出は必須で、ミスがあると登記できません。
資本金1円の会社でも定款認証(株式会社は約5万円)、登録免許税(合同会社は約6万円・株式会社は約15万円前後)、印鑑作成費用などの設立費用は別途必要です。そのため、実際には30万円前後の設立資金が必要になることが一般的です。
1円は設立時の資本金であり、実際の事業活動や経費支払には十分な運転資金が必須です。手元資金不足では資金繰り難や信用力不足で融資・許認可取得に不利になるため、自己資金や調達計画を持つ必要があります。

1円起業の手続き方法は、会社形態の選択から登記・各種届出まで段階的に進めていきます。ここでは、主要な手順や注意点を解説します.
「株式会社」は設立費用・社会的信用は高いですが、定款認証やガバナンス上のルールは複雑です。設立費用は約22万円~25万円が一般的でしょう。
一方、「合同会社」は運営が柔軟で設立時の費用(約6~10万円)が安く・定款認証不要など手続きが簡単です。事業計画や規模、将来の資金調達・ステータス重視度によって最適な会社形態を選択しなくてはなりません。
会社設立時は、商号・事業目的・本店・発起人・資本金額など主要ルールを記載した「定款」を作成する必要があります。株式会社では定款認証が必要(公証役場での認証費用は1.5~5万円)ですが、合同会社は不要です。
定款認証時は、絶対的記載事項(目的、商号、本店、発起人、出資額等)を漏れなく記載しなくてはなりません。
設立登記は、定款認証後に主な必要書類(登記申請書、資本金払込証明書、印鑑届出書、印鑑証明書、代表者住民票など)を法務局へ提出します。資本金1円でも登録免許税(株式会社最低15万円、合同会社6万円)がかかるため注意が必要です。
書類・費用面の不備があると登記できないため、事前に十分確認しましょう。
起業する際には、税務署へ「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などを提出する必要があります。都道府県税事務所・市区町村へも法人設立届けを行い、社会保険や労働保険は年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの手続きも必要です。

1円起業の主なメリットは、以下のとおりです。
| ・少ない資金で起業できる ・起業のハードルが下がる ・融資や補助金を活用できる |
ここから、それぞれについて解説します。
最低資本金制度が撤廃され、1円から会社の設立ができるため、自己資金や出資者が少なくても起業することが可能です。これまでの株式会社設立では1,000万円以上の資本金が必要でしたが、現在は大幅にハードルが低くなっています。
少額資本で法人登記できるため、ビジネスアイデアを持つ個人でも起業しやすく、心理的ハードルも低くなるのが1円起業のメリットです。失敗しても再挑戦しやすい環境が整い、ベンチャーやスモールスタートにも適しています。
法人格を持つことで、個人事業主よりも融資や補助金申請の対象となるケースが増えるのもメリットです。資本金1円でも、事業計画や将来性次第で自治体や金融機関の支援を受けやすくなり、資金調達の幅が広がります。
また資本金1,000万円未満の会社は、設立後の数年間消費税免除など税制優遇も得られます。
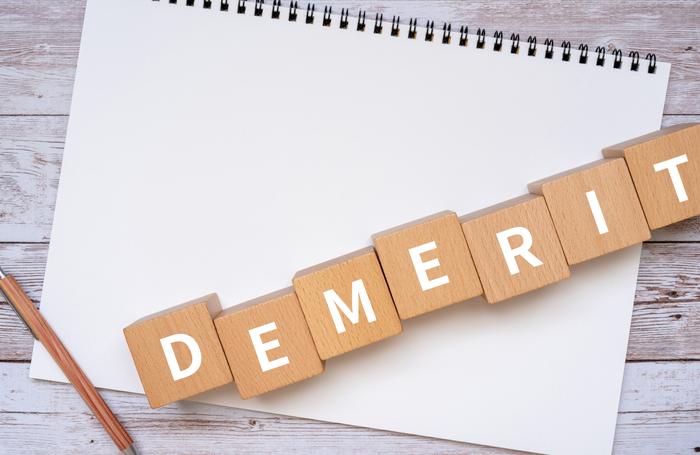
1円起業には、以下のデメリットもあるため注意が必要です。
| ・信用力不足 ・運転資金不足リスク ・資本金増資が必要になるリスク |
ここから、それぞれの内容を確認しておきましょう。
資本金1円では「財務基盤が脆弱」「事業継続の信頼性が低い」とみなされるため、取引先や金融機関からの信用が得られにくくなるのがデメリットです。法人口座の開設拒否や融資審査で不利になるほか、業種によっては許認可が得られにくい場合もあるでしょう。
資本金1円では、創業期の必要経費や設備投資、運転資金を十分に賄えないため、資金繰り悪化のリスクが高まります。取引先への支払いや予想外の支出が発生した際、資金不足で事業が立ち行かなくなるケースもあるでしょう。
信用力や資金力が不足すれば、後々増資が必要となり、資本金額を引き上げるための事務やコストが追加で発生します。特に、金融機関からの融資や新規大口取引の際は、資本金を一定以上に増やすよう求められる可能性が高いでしょう。

1円起業で気をつけるべき注意点は、資金繰りの確保、資本金額が信用力に直結する点、税務・社会保険負担への事前理解、そして事業計画の重要性です。ここから、それぞれ解説します。
資本金が少ないと事業開始後に運転資金が不足し、個人資産から持ち出しが必要になるケースが多い傾向です。融資や資金調達も難しく、赤字や想定外の支出による倒産リスクが高まるため、最低でも数か月分の運転資金準備が欠かせません。
資本金額は登記簿に明記され、取引先や金融機関も確認するため、極端に少額の場合は「信用力不足」と判断されやすいでしょう。法人口座開設が難しくなる場合や、許認可業種では資本金額が審査条件になることもあります。
法人設立後は、法人住民税の均等割や社会保険・労働保険など、赤字でも必ず発生する固定負担があります。小規模資本でも税務申告・社会保険対応は欠かせず、年数十万円以上のランニングコストを見込んでおかなくてはなりません。
資本金が少なくても、綿密な事業計画と集客目処があればリスクを大きく減らせます。設備・在庫投資、集客・売上獲得までの資金繰りを事前にシミュレートし、必要に応じて増資や専門家サポートを活用すべきです。

1円起業は、小規模で初期投資の少ないITやサービス業に向いています。一方、設備投資や信用力が重視される業界には不向きです。以下で、それぞれの詳細について解説します。
IT系、Webサービス、コンサルティング、ライター、デザイナーなど、事務所不要・在庫不要・少額資金で始められる事業が1円起業に向いています。個人のスキルやデジタル資産を活用するビジネス、ネットビジネス、フリーランス・オンラインサービス、軽貨物運送なども低資本で可能です。スモールスタートや事業検証、リスク分散を重視する起業家に適しているでしょう。
製造業、建設業、飲食店など、設備・店舗・在庫が必要な業種は初期投資が大きく1円起業には不向きです。信用力重視の業界(金融・保険・中古車販売・宅建業など)や、許認可取得に資本金額要件がある業種は最低資本以上が求められます。融資や取引先からの信頼が必要な業界、大口契約や法人口座開設が重要な業種では資本金を多く設定する方が安全です。

1円起業は、会社法改正により資本金1円から会社設立が可能になった制度です。少額で起業できる一方、実際には設立費用や運転資金が必要で、信用力不足などのリスクもともないます。ITやサービス業など小規模ビジネスには向きますが、設備投資や信用が重視される業種には不向きです。税理士などの専門家にも相談し、資金計画と事業計画を十分に立てたうえで検討しましょう。
税理士を探す際には、税理士紹介ドットコムの活用がおすすめです。手数料なども一切不要で、北海道から沖縄まで、全国のご希望のエリアで税理士をご紹介することが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。