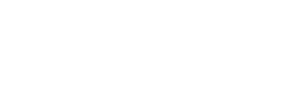
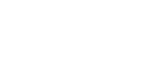

中小企業経営者にとって「廃業かM&Aか」は大きな経営判断です。どちらを選ぶべきか迷う背景には、費用や手続き、従業員や取引先への影響、そして事業価値を残せるかどうかがあります。ここでは、廃業とM&Aの基本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、費用や判断基準までをわかりやすく解説し、最適な選択肢を検討するためのヒントをご提供します。
目次

廃業とM&Aは、「事業を消すか」「事業を譲るか」という点が根本的な違いです。ここでは、それぞれの定義や手続きの流れ、違いを解説します。
廃業は、経営者が自らの意思で事業活動を全面的に終了し、会社の法人格を法的に消滅させる手続きです。主な手続きは、営業終了日の決定、従業員や関係者への通知、株主総会での解散決議、法務局への解散登記、債権者保護手続き、税務署への申告、会社資産の売却・債務弁済・残余財産分配、最後に清算完了登記を行い、関係機関へ届出を提出する流れです。
廃業後、長年培ってきた事業の歴史や技術、雇用、取引先との関係は消失します。
M&A(Mergers and Acquisitions)は、企業の合併や買収を指し、事業そのものや会社を第三者へ譲渡することで事業を残す取引です。手続きは、M&A仲介会社への相談から始まり、相手企業の選定、企業価値評価、スキーム選択、基本合意・条件交渉、デューデリジェンス(精査)、最終契約締結、クロージング(引渡し)を経て、その後の統合作業へと進みます。
一般的に従業員の雇用や取引先との関係も維持され、会社・事業は新しい経営者の元で継続されるのが特長です。
廃業は事業活動の「消滅」選択で、会社や事業が社会的に終焉することを意味します。一方、M&Aは事業を「譲渡」して第三者の手に引き継ぐ選択肢で、事業のノウハウや雇用、企業ブランドなどを存続・発展させることが可能です。
両者は「事業継続性」がもっとも根本的な違いであり、それにともなう経営者の得る対価、従業員や取引先の将来も大きく異なります。

廃業には、経営者のリスク解消やシンプルな出口戦略などのメリットがある一方、従業員や取引先への影響、清算コスト発生、資産価値喪失といったデメリットもあります。ここから、廃業の主なメリット・デメリットを確認しておきましょう。
廃業のメリットは、以下のとおりです。
| ・経営リスクの解消 ・シンプルな出口戦略 ・後継者不要 |
廃業により、会社経営にともなう負担や精神的ストレスから解放され、将来の追加損失リスクも回避可能です。また、清算処理によって破産手続きより簡素に事業を終了でき、短期間で撤退できます。
後継者問題に悩むことなく会社を法的に消滅でき、経営者個人の資産保全にも有用です。
また、関係者への迷惑を最小限に抑える(債務の返済で負担を残さない)、法人税・住民税など実質的な負担も回避できます。
廃業の主なデメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
| ・従業員・取引先への影響 ・清算コスト発生 ・資産価値の喪失 |
廃業によって雇用が失われ、従業員やその家族は生活基盤を失うのはデメリットです。また、取引先は取引減少や経営悪化のリスクが生じ、場合によっては連鎖廃業を招くこともあります。
登記費用、官報公告費、清算手続き費用など一定のコストが発生し、状況によっては資産売却の損失も生じることがあるでしょう。長年培った技術、ノウハウ、ブランドなどの無形資産、事業資産が全て消滅し、後に再活用することは困難です。さらに許認可の喪失、新規事業開始時には再取得コストも必要です。
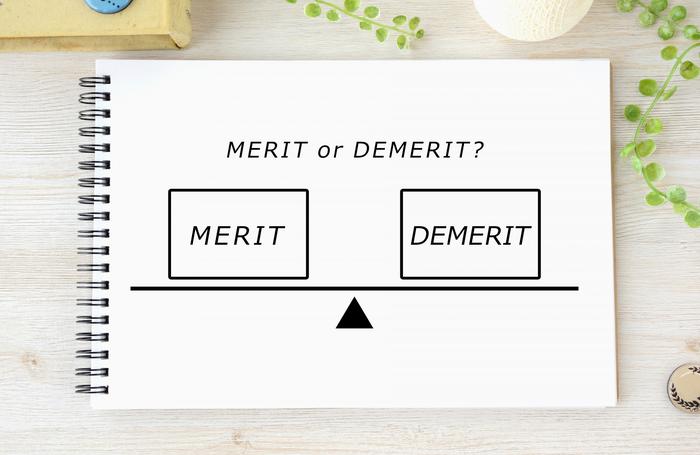
M&Aのメリットは事業承継や売却益の獲得、従業員の雇用維持などが挙げられます。一方で、手続きが複雑で、買い手が見つからないリスクや交渉期間の長期化などのデメリットもあります。以下で、それぞれ解説します。
M&Aの主なメリットは、以下のとおりです。
| ・事業承継が可能 ・売却益の獲得 ・従業員の雇用維持 |
M&Aは、後継者がいない場合でも第三者へ事業を譲渡でき、事業価値・ノウハウ・技術・ブランドなどを次世代へつなげられるのがメリットです。経営者は事業譲渡の対価として売却益を得て、リタイア後の生活資金や新たな挑戦への原資を確保できます。
また、M&Aは会社自体が消滅するわけではないため、従業員は新経営体のもとで雇用が維持されるケースが多い傾向です。さらに、企業規模拡大や新規事業参入、基盤強化など買い手側にも時間効率や競争力向上のメリットも得られます。
M&Aを行う際には、以下のデメリットに注意が必要です。
| ・手続きの煩雑さ ・買い手が見つからないリスク ・交渉期間の長期化 |
M&Aを行う場合、相手探しや条件交渉、企業価値評価、契約や統合準備など多くの工程があり、書類や審査も多岐にわたるのが特長です。希望条件を満たす買い手がなかなか見つからない場合、話が進まず廃業に至るケースもあります。
また、M&Aプロセスは数か月〜1年以上かかることも珍しくなく、途中で破談になる可能性も高めです。組織文化や業務体制の統合には計画的な対応が必要で、従業員・取引先の混乱や企業価値の毀損リスクがともないます。

廃業とM&Aは、かかる費用や期間、専門家の関与度が大きく異なります。ここから、それぞれの詳細を解説します。
廃業を行う場合、法的な手続き費用(登記費用約41,000円、官報公告費約40,000円など)が必要です。その他、設備や在庫の処分費用、原状回復費、従業員への退職金・社会保険手続きなど、実務的な費用が大きく変動します。
規模が大きい場合は数十万円~数百万円かかることもあり、個人事業ならほぼ0円で済むケースもあるでしょう。廃業完了までの期間は「最短でも2か月以上」ですが、資産処分や債権者との調整等で長引く場合もあります。
M&Aを行う際、仲介会社への着手金(50万~200万円が相場)、成功報酬(譲渡価格の数%)、デューデリジェンス(企業調査)費用、契約・登記費用などが発生するのが一般的です。さらに買い手側は買収価額、売り手側は譲渡対価を得ますが、手続き全体に各種専門家の費用も発生します。
M&Aの期間は一般的に3~6か月、場合によっては1年以上かかることもあります。
廃業では税理士・司法書士・社会保険労務士が登記や税務、労務手続きで必要となる場合があります。M&Aの場合は、M&A仲介会社、公認会計士・弁護士など複数の専門家の関与が不可欠で、最適な相手探しや契約交渉、法務・財務調査において非常に重要な役割を果たします。

廃業とM&Aは、経営状況や事業の価値、従業員や取引先、売却益や将来価値の重視度によって選択の判断基準が大きく異なります。ここでは、選ぶときの基準を解説します。
赤字が継続し、債務超過で事業再建の見込みがない場合は、迅速な廃業を選ぶ方が現実的です。安定した収益や将来性、独自技術・顧客基盤等の事業価値がある場合はM&Aで売却できる可能性があります。
したがって、一時的な赤字でも改善可能性があれば、M&A交渉による事業継続や再生も選択肢となりえるでしょう。
雇用・取引先維持を重視する場合はM&Aが最適です。買い手企業が事業・従業員・取引関係を引き継ぐケースが多く、従業員の雇用や長年の取引先との信用も守られます。
廃業では原則全従業員解雇、取引停止となるため、これらへの影響が大きい傾向です。
従業員や取引先に優れたノウハウや信用財産がある場合も、譲渡(M&A)の方が社会的影響を最小限に抑えられます。
売却益や無形資産の最大化を重視する場合はM&Aが有利でしょう。廃業では清算価値のみの評価となる一方、M&Aでは事業全体の価値(ブランド・技術・顧客基盤等)が評価され、多くの資産が残る可能性が高いためです。
M&A成立時には、譲渡益によるリタイア資金や新規挑戦の原資確保も可能です。廃業は早期・簡便ですが、資産・将来価値を残すより「リスク遮断」を優先するケースで選ばれます。

廃業やM&Aを検討する際は、早めの準備、専門家による助言、税務・法務面の十分な確認が重要です。ここでは、それぞれの注意点を解説します。
廃業やM&Aは意思決定から実際の完了まで半年以上かかる場合があり、後継者不足や業績悪化を感じた段階で早期に検討を始めることが重要です。
特にM&Aは相手探しや条件交渉、デューデリジェンス(財務・法務調査)に時間がかかるため、遅れが致命的な結果を招くこともあります。廃業の場合でも、従業員や取引先への通知や影響の説明など、周囲への調整を早めに行わなくてはなりません。
廃業・M&Aの判断では、税理士や弁護士、公認会計士、M&A仲介会社など専門家への相談が必須です。財務分析、税務リスク、法的手続き、など幅広い知識が必要なため、経験や実績豊富な専門家サポートで最善策を見極めることが成功の鍵といえるでしょう。
M&A仲介業者は買い手探しや契約交渉だけでなく、手続きや統合後のサポートも行います。
廃業は法人税・清算所得税・株主配当課税など、二重課税に近い形で高い税負担が発生します。M&A(特に株式譲渡型)の場合、譲渡所得に対する分離課税(約20%)となり、税負担が軽減できるケースが多い傾向です。
法的には簿外債務や未解決の訴訟・契約不備などを引き継ぐ場合があり、事前のデューデリジェンスが欠かせません。廃業・M&Aいずれの場合も、法令遵守や全関係者への適切な通知・説明といったコンプライアンス意識が求められます。

廃業は事業を消滅させる選択でリスク解消や簡便さがメリットですが、雇用喪失や資産価値消滅がデメリットです。一方、M&Aは事業を譲渡して継続でき、売却益や雇用維持が可能ですが、手続きの複雑さや買い手不在のリスクがあります。費用・期間・税務面も異なるため、経営状況や従業員・取引先への影響、将来価値を重視して最適な選択を検討することが重要です。
また、実際には廃業やM&Aを実施する際には、税理士などの専門家への相談も視野に入れる必要があります。
税理士を探す際には、税理士紹介ドットコムの活用がおすすめです。手数料なども一切不要で、北海道から沖縄まで、全国のご希望のエリアで税理士をご紹介することが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。