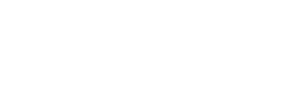
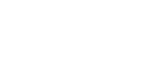

起業は夢の実現への第一歩である一方、多くの企業が数年以内に姿を消しているのも事実です。実際、日本では起業後数年で、多くの企業が倒産に至っています。
本記事では、起業後の企業生存率をデータに基づいて解説するとともに、倒産に至るおもな理由や、長く事業を継続するために押さえておきたいポイントをご紹介します。起業を検討している方、事業継続に不安のある方はぜひご参照ください。
目次

会社を起業した後、実際にはどの程度の期間、存続できるものなのでしょうか。ここでは、期間ごとの企業生存率を解説します。
企業生存率とは、起業・創業した企業が廃業や倒産をせずに経営を継続できている割合を示す指標です。法人を対象とし、個人事業主は含まれません。企業の安定性や市場環境を把握する上で重要なデータです。
企業生存率は、起業からの経過年数ごとに大きく変動します。日本の企業生存率は、欧米諸国と比較して高い水準にありますが、年数が経過するごとに徐々に低下していく傾向です。その背景には日本の開業率の低さや、経営環境の変化、後継者不足などの要因が影響しています。
ここからは、期間ごとの企業生存率をご紹介します。
日本における起業後5年以内の企業生存率は、以下のとおりです。
| ・1年後:95.3% ・3年後:88.1% ・5年後:81.7% |
日本では5年以内に約18%の企業が廃業や倒産を経験していることがわかります。なお、同じ5年後の生存率はアメリカ48.9%、イギリス42.3%、ドイツ40.2%、フランス44.5%と、海外と比較して日本は高い水準です。
起業後10年の企業生存率は、一般的な中小企業で70~72%程度です。つまり、10年間で約3割の企業が市場から退出しています。ベンチャー企業に限ると生存率はさらに低下し、6.3%程度まで下がるというデータもあります。
起業後20年以上の企業生存率は約54%です。さらに30年後には43%、36年後には46%程度です。20年以上存続する企業は半数程度に減少しますが、一定数の企業は長期にわたり事業を継続しています。

起業後、倒産に至る理由は多くありますが、おもなものは以下のとおりです。
| ・販売不振(売上の低迷) ・資金計画の甘さ・過小資本 ・放漫経営(経営管理の甘さ) ・既往のしわよせ(過去の資産頼み・経営改善の先送り) ・主要取引先との取引終了・連鎖倒産 |
ここから、それぞれの内容を解説します。
起業後に倒産する理由として、もっとも多いのが販売不振です。思うように商品やサービスが売れず、売上が上がらないことで資金繰りが悪化し、経営が成り立たなくなるケースです。
売上の減少が徐々に進む場合もあれば、急激に減少する場合もあり、特に急減時には迅速な対応が求められます。市場や顧客ニーズの変化に対応できない、不十分なマーケティングなどがおもな理由です。
起業時に資金計画が不十分なことや、資本金が少なすぎる場合、予期せぬ出費や売上不振に耐えられずに資金ショートを起こす可能性が高くなります。初期の売上が計画よりも低かった場合も、固定費や人件費は発生し続けるため、資金繰りに行き詰まりやすいでしょう。
特に飲食業などでは、開業後数か月で閉店に追い込まれるケースも多くみられます。
経営者が独善的な判断をしたり、会社を私物化したりすることで、経営が混乱し、倒産に至るケースも多い傾向です。ワンマン経営や同族経営に多くみられ、内部統制が効かずに無計画な投資や無駄な支出が増えることで、経営が悪化します。
また、ずさんな管理体制は従業員による不正の温床にもなり、企業の体力を奪ってしまうため注意が必要です。
過去の実績や資産に頼り、現状の経営悪化に目を向けず、具体的な改善策を講じないまま資産を食いつぶしてしまうケースも、倒産に至る理由の1つです。
業績が悪化しても「今まで何とかなったから」と現実を直視せず、抜本的な改革を怠ることで、いずれ資金が底をつき廃業に追い込まれます。
特定の取引先に売上を依存している場合、その取引先との関係が終了すると売上が大きく減少し、事業継続が困難になることもあります。
また、取引先企業の倒産などによる「連鎖倒産」も倒産理由の1つです。短期間で売上回復が見込めない場合、廃業を決断する経営者も多く存在します。

会社を倒産させず、長期間継続させるためには、以下の5つのポイントを押さえることが重要です。
| ・資金を十分に確保・管理する ・会社独自の強みを明確にし、活かす ・時代のニーズや市場変化に合わせて改善・適応する ・早期から後継者教育や事業承継の仕組みを整える ・経営知識やノウハウを学び続ける |
ここから、各ポイントの内容を解説します。
会社が長く存続するためには、安定した資金繰りが何よりも重要です。起業時には初期投資や運転資金を十分に確保することが求められますが、創業後も事業が軌道に乗るまでの間は予想外の出費や売上の変動が発生しやすく、資金不足に陥るリスクが高まります。
また、景気の変動や取引先の倒産など、外部環境の変化による一時的な売上減少にも備えなくてはなりません。日頃からキャッシュフローをしっかりと管理し、無駄なコストの削減や、必要に応じて融資や補助金の活用も検討すべきです。資金繰り表の作成や定期的な見直しを行い、資金ショートの兆候を早期に発見して対策を取ることが、会社の安定経営につながるポイントです。
長く続く会社には、他社にはない「独自の強み」が存在するケースが多い傾向です。特許技術や独自のノウハウ、高品質なサービス、地域密着型の営業力、あるいはブランド力など、さまざまです。自社の強みを明確にし、それを最大限に活かした商品・サービス展開を行うことで、他社との差別化が図れ、顧客からの支持を長期的に得られるでしょう。
また、強みを活かすことで価格競争に巻き込まれにくくなり、安定した利益を確保しやすくなります。定期的に自社の強みや弱みを分析し、強みをさらに磨き上げていく姿勢が大切です。
社会や市場のニーズは常に変化するものです。創業時にうまくいったビジネスモデルや商品も、数年後には時代遅れになる可能性があります。そのため、顧客の声や市場動向を敏感にキャッチし、必要に応じて商品やサービス、ビジネスモデルを柔軟に改善・改良していくことが不可欠です。
例えば、IT化やデジタル化の波に乗り遅れると、競合他社に大きく差をつけられてしまうこともあるでしょう。定期的に市場調査を行い、時代の変化に合わせた新しい取り組みやサービスを導入することで、常に顧客から選ばれる企業であり続けられます。
会社を長く続けるためには、経営者自身だけでなく、次世代を担う後継者の育成や事業承継の準備が非常に重要です。特に中小企業では、後継者不足が深刻な問題となっており、せっかく築き上げた事業も、後継者がいないために廃業せざるを得ないケースが増えています。早い段階から後継者候補を見つけ、経営に関する知識や現場経験を積ませることが大切です。
また事業承継の際には、株式や資産の分配、税金対策、従業員や取引先への説明など、さまざまな課題があります。これらを計画的に準備し、スムーズなバトンタッチを実現することで、会社の永続性を高めることが可能です。
経営環境は日々変化しており、昨日までの成功パターンが明日も通用するとは限りません。経営者や幹部が常に新しい知識やノウハウを学び続けることで、時代の変化に対応し、的確な経営判断を下せます。例えば、経営セミナーへの参加や、専門書の読書、他社の成功事例の研究など、さまざまな方法で学びの機会を持つことが大切です。
また、社内でも従業員の教育やスキルアップを促進し、組織全体のレベルアップを図ることで、競争力の維持・強化につながるでしょう。学び続ける姿勢が、会社の成長と安定経営の原動力といえます。

起業後の企業は年数の経過とともに生存率が低下し、資金不足や販売不振、経営管理の甘さなどが倒産のおもな原因です。長く事業を続けるためには、資金管理や独自の強みの活用、市場変化への対応が欠かせません。また、税務面の不安がある場合は、専門家のサポートを受けることが有効です。
税理士を探す際には、税理士紹介ドットコムの活用がおすすめです。手数料なども一切不要で、北は北海道から南は沖縄まで、全国ご希望のエリアで税理士をご紹介することが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。